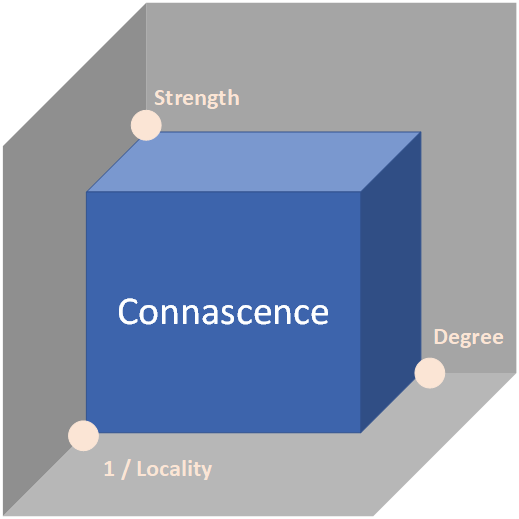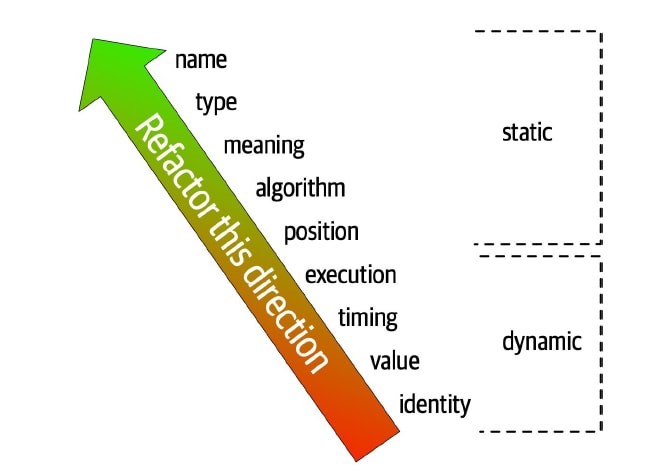翻訳を担当した書籍『ユニコーン企業のひみつ―Spotifyで学んだソフトウェアづくりと働き方』(オライリー・ジャパン)が4月26日に発売になります。本書は2019年3月にPragmatic Bookshelfより出版されたJonathan Rasmusson著『Competing with Unicorns: How the World’s Best Companies Ship Software and Work Differently』の全訳です。
本書は、『アジャイルサムライ』(オーム社、2010年)の著者として日本でもよく知られている、Jonathan Rasmussonの3冊目の著作であり、ある時期のSpotifyに身を置いていた著者が、そこでの経験などを元にユニコーン企業のソフトウェアづくりと働き方について解説した書籍となります。
大規模な成功を収めているテック企業(ユニコーン企業)は、スタートアップで機能していたテクニックをエンタープライズ企業レベルにまでスケールさせる方法を見いだし、日々実践しています。Amazon、Facebook、Googleなどは、何万人もの従業員を抱えているにもかかわらず、スタートアップのように働いています。本書はSpotifyでアジャイルコーチやエンジニアの経験を持つ著者がユニコーン企業のソフトウェアづくりと働き方を解説します。 ミッションによってチームに目的を持たせ、スクワッドに権限を与え、信頼する。カンパニーベットを通じて大規模な取り組みを調整する。このような働き方とそれを実現するための文化のあり方を解説し、複数チームが連携しながら質の高いプロダクトを早くリリースし、迅速に技術革新を行うための方法を学びます。 プロダクトのデリバリーにフォーカスする世界有数のテック企業の事例を紹介する本書は、デリバリープロセスやプロダクト組織自体を改善したいエンジニアやマネージャー、経営リーダー必携の一冊です。
この書籍紹介を読むと、もしかすると「ああなんだ、Spotifyモデルの話か」と思われる方もいるかもしれません。もし、そう思われた方がいたら、いったんその予備知識を傍に置いて、本書を手にとっていただけたら幸いです。そうした捉え方で本書を読んでしまうと、おそらく本書が伝えている大事な部分がこぼれてしまうと考えているからです。
本書は、単に「Spotifyモデル」を解説した本ではありません。本書は、Spotify(をはじめとするテック企業)がどうやってエンジニアリング組織の運営に取り組んでいて、その根っこには何があるのかを捉えようとした書籍です。
本書への推薦の言葉
日本の読者の皆さんへ
お目にかかれて光栄です
1章 スタートアップはどこが違うのか
1.1 スタートアップは「火星」から来た
1.2 「学習する機械」
1.3 エンタープライズ企業は「金星」から来た
1.4 「期待に応じる機械」
1.5 つまり、こういうことだ
1.6 "Think Different"
2章 ミッションで目的を与える
2.1 プロジェクトの問題点
2.2 これが「ミッション」だ
2.3 ミッションはチームの自発性を高める
2.4 ミッションは目的を意識させる
2.5 ミッションは仕事そのものにフォーカスさせる
2.6 ミッションの例
2.7 目的を与えよう
3章 スクワッドに権限を与える
3.1 スクワッドとは?
3.2 スクワッドはどこが違うのか?
3.3 プロダクトマネージャー
3.4 データサイエンティスト
3.5 分離されたアーキテクチャ
3.6 自律、権限、信頼
3.7 経営リーダーのためのヒント
3.8 Q&A
3.9 権限を与える
4章 トライブでスケールさせる
4.1 スケーリングの課題
4.2 スケーリングの原則
4.3 トライブ、チャプター、ギルド
4.4 トライブ
4.5 チャプター
4.6 ギルド
4.7 どこで働きたい?
4.8 Q&A
4.9 スケールは大きく、チームは小さく
5章 ベットで方向を揃える
5.1 しおれた百の花
5.2 カンパニーベットとは
5.3 カンパニーベットの仕組み
5.4 この働き方の見事なところ
5.5 やり抜くためのコツ
5.6 ベットに賭けろ
6章 テック企業で働くということ
6.1 フラット化する世界
6.2 「何をすべきかを指示するつもりはないよ」
6.3 お金の使い方が違う
6.4 「信頼してないの?」
6.5 すべての情報は基本的にオープン
6.6 「手伝おうか?」
6.7 テック企業流の人の動かし方
7章 生産性向上に投資する
7.1 プロダクティビティスクワッドを編成する
7.2 セルフサービスモデルを採用する
7.3 ハックウィークを開催する
7.4 技術に明るいプロダクトオーナーを活用する
7.5 品質に高い期待を持つ
7.6 社内オープンソースを活用する
7.7 あらゆるレベルでの継続的な改善
7.8 フィーチャーフラグを活用する
7.9 リリーストレインでリリースする
7.10 技術を「一級市民」として扱う
8章 データから学ぶ
8.1 どこにでもデータがある
8.2 プロダクトを計測する
8.3 A/Bテストで実験する
8.4 そこでデータサイエンティストですよ
8.5 データを活用する
9章 文化によって強くなる
9.1 会社が違えば文化も違う
9.2 Spotifyの文化
9.3 良い文化ってどんな感じ?
9.4 核となる信念
9.5 行動は言葉に勝る
9.6 スウェーデンっぽさ
9.7 文化が重要
10章 レベルを上げる:ゆきてかえりし物語
10.1 目的で動機づける
10.2 思考は戦略的に、行動は局所的に
10.3 プロジェクトではなくチームに投資する
10.4 技術を「一級市民」として扱う
10.5 もっとスタートアップみたいに振る舞う
10.6 自律した小さなチームとともに
10.7 コンテキストもあわせて取り入れる
10.8 率先垂範のリーダーシップ
10.9 権限を与え、信頼する
10.10 「言い訳」を取り除く
10.11 最後に
訳者あとがき
索引
「Spotifyモデル」と聞くと、あたかもそういう「定まったもの」があるように感じ、それをやる・やらない、それが良い・悪い、といった見方をしてしまいがちです。ですが、Spotifyの人たちは、そういう定まったものをあらかじめ持っていたわけでも、それを定めることを目的に何かをしていたわけでもありません。彼らがしていたこと、そして現在でもしていることは「自分たちにとって最善なエンジニアリング組織運営とはどういうものか」に対する取り組みの試行錯誤(学習と実験)だけです。
事業サイズ、従業員規模、プロダクトの状況、解くべき問題が変われば、取り組みも変わっていきます。つまり、巷で言われているSpotifyモデルとは、彼らのそうした組織運営に対する取り組みの、ある時点でのスナップショットに過ぎません。
本書の内容でそれよりも重要なのは、彼らがなぜそうした取り組みに辿り着いたのか、そして、どんな組織であるからこそそうした取り組みが可能なのか、です。
その鍵となるのは、組織が大事にしている価値、そして文化です。何を価値ととらえ、文化をどう育てていっているのか、そこに「ユニコーン企業のひみつ」があります。
何を自分たちの問題ととらえ、それを解決するためにどういうアプローチを取るのか、そしてそれはなぜか。自分たちは何者なのか。そうした厳しい問いの先に、それぞれの企業の組織運営プロセスは現れます。そして、私たちも、そうした厳しい問いの先で、自分たちのプロセスを見つけていく必要があります。
本書は、そうした手ごわい仕事に向かうにあたってのヒントとなる1冊です。
とはいえ、そこはJonathanの著作。アジャイルサムライよろしく、本書も楽しく読める一冊に仕上がっています。
本書は、前書きのこんな結びとともに始まります。
"READY PLAYER ONE?"
VRゴーグルをつけて、いざユニコーンの住む世界へ。深刻になり過ぎずに楽しく読んでいただけたら幸いです。

ユニコーン企業のひみつ ―Spotifyで学んだソフトウェアづくりと働き方
- 作者:Jonathan Rasmusson
- 発売日: 2021/04/26
- メディア: 単行本(ソフトカバー)